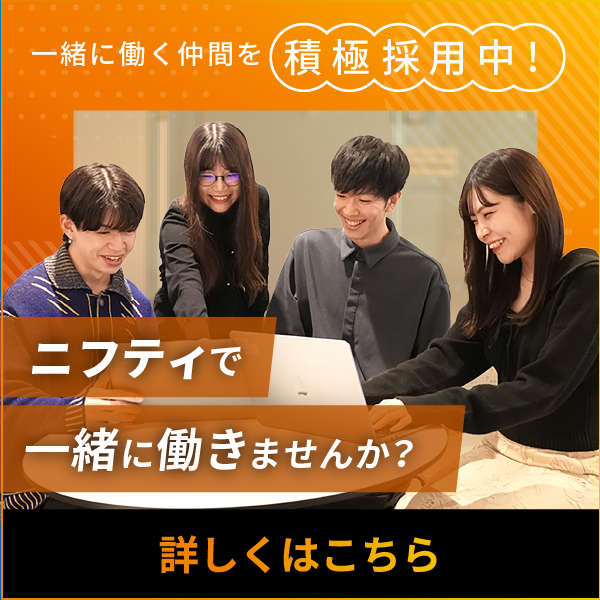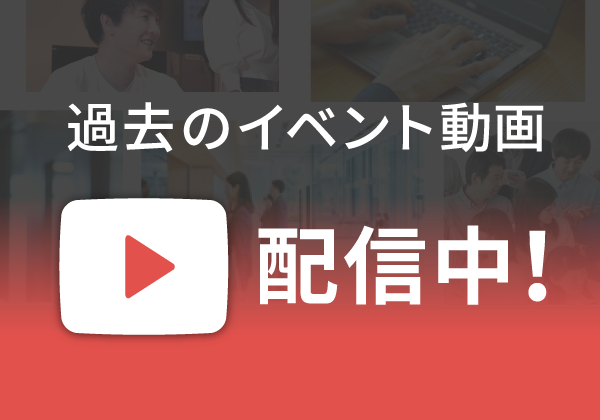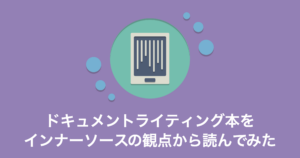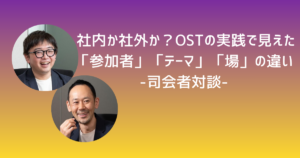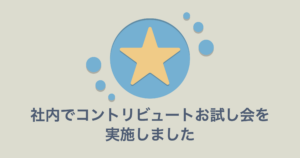はじめに
こんにちは。瀧山・添野です。
本記事は、InnerSource Commonsが、9/12に主催したInnerSource Gathering Tokyo 2025の参加レポートになります。
InnerSource Gathering Tokyo 2025とは
InnerSource Commonsというインナーソースに関するナレッジの創出と共有に特化したコミュニティがあり、そのコミュニティの日本支部が9/12にdocomo R&D OPEN LAB ODAIBAで実施したイベントになります。
弊社のメンバーがInnerSource Commonsに所属しており、本イベントでは運営や配信機器に関わるスタッフとしても参加いたしました。
イベントのHPはこちら
https://gatherings.innersourcecommons.org/tokyo-2025/
配信機器に関わるスタッフはこちら
なぜ参加したのか
瀧山:私はまだインナーソースを実践できていないので、インナーソースのベストプラクティスに興味がありました。また、ニフティを退職された方が一般参加されていたので、単純にその方に会いたいという理由もありました。
添野:私は、現在社内でインナーソースを推進するメンバーの一人で、本イベントのスタッフであった上司や同僚からも誘われて参加いたしました。
本題
イベント参加特典
本イベントに参加したところ、以下のものをいただきました。
- インナーソースヒーローのステッカー×2
- インナーソースヒーローのハンカチ
- InnerSource Commonsのロゴステッカー×2
- 水
※インナーソースヒーローとは、InnerSource Commons Japanで生まれたキャラクターです。
詳細は、昨年のこちらのセッションをご確認ください。
https://youtu.be/ynlGpNnTCkc?si=K5nXXPnOwaKvB5Mi

セッション
Welcome to InnerSource Gathering Tokyo 2025
イオンスマートテクノロジー株式会社 / InnerSource Commons Foundation
久保 翔馬 (Shoma Kubo) 様
「インナーソースとはなにか」や「チャタムハウスルール※」の説明がありました。
※チャタムハウスルールとは、会議で得た情報を自由に利用できるが、発言者の身元や所属、参加者の身元を明らかにすることはできないという、議論の自由な参加を促すための会議ルールです。
会場ご案内
[会場スポンサー] 株式会社NTTドコモ
本イベントの会場であるdocomo R&D OPEN LAB ODAIBAについての説明がありました。
本会場は、執筆時点(2025年9月)では、ドコモグループ社員と一緒であれば、今回のようなオープンなイベントを平日に実施できるイベント会場とのことでした。
また非イベント時では、コワーキングスペースとしても利用できるようです。
詳しくはHPをご確認ください。
https://docomo-openlab.jp/about/
本イベントを実施したエリアでは、壁一面にディスプレイがあり、また座席の上部数カ所にもモニターが用意されており、非常に見やすい会場でした。
インナーソースで未来を築こう
ワイクル株式会社 代表取締役
角 征典 (Masanori Kado) 様
資料:https://kdmsnr.com/slides/20250912_innersource/
インナーソースへの認識合わせから始まり、インナーソースに参加する動機や、組織に効果的に普及させるための実践的なアプローチについて解説されました。
インナーソースへの認識合わせのパートでは、ファイルを触らない貢献の例が話されており、貢献のレビュー、貢献のテスト、イシューのトリアージを例として出ていました。
※登壇者の角さんの書籍はこちらになります。
感想
瀧山:
- OSSからインナーソースへと繋がる歴史が興味深かったです。
- 参考文献も多数紹介されており、OSSやインナーソース関連の書籍で勉強してみたいと思いました。
添野:
- 貢献のレビューで出ていた「送信は厳密に、受信は寛容に」というポステルの法則が響きました。
- またイシューのトリアージは、普段コードを触らない方でも簡単に実践できそうでしたので、社内でも実践してみようと思います。
- 組織に効果的に普及させるための実践的なアプローチについて話されていた体験談では、感情も含めた共有が良いという内容で、参考になりました。
InnerSource活動『xPalette(クロスパレット)』が解き放つエンジニアの創造性と主体性
野村総合研究所 生産革新センター プラットフォームサービス開発二部
昼間 貴宏 (Takahiro HIRUMA) 様
xPaletteは、開発現場を業務ロジックの開発に集中できる快適な環境にすることを目的とした開発コミュニティです。立ち上げ時1人から16人まで成長した過程で培った、エンジニアの主体性を引き出すコミュニティ運営の工夫や、インセプションデッキを活用した共鳴の強化などの実践的な取り組みが紹介されました。
感想
瀧山:
- 社内の複数プロジェクトで使うガイドラインや共通テンプレートのようなものがインナーソースに合っているのかなと感じました。
添野:
- 主体的に活動したくなるコミュニティを目指すという方向性は非常に理にかなっていると感じました。
- また、インセプションデッキを定期的に実施されているのも素晴らしい取り組みだと思いました。
三菱電気が推進するInnerSourceの未来
三菱電機株式会社 設計技術開発センター オープンソース共創推進部 部長
追立 真吾 (Shingo Oidate) 様
三菱電機では、OSSの開発や利用などを管理・推進する組織を2025年4月に新設されたとのことでした。オープンソースとインナーソースの両方を推進することで相乗効果を目指されているそうです。
また社内では、次のセッションでご登壇された小林様や、InnerSource Commons japanの服部様をゲストにお招きし、インナーソースDayを開催されたということでした。
感想
瀧山:
- OSSやインナーソースを推進する専門の部署があるのはすごいと感じました。なかなかここまでやっている会社はないと思います。
添野:
- オープンソースとインナーソースの両方を推進するアプローチは非常に興味深いと感じました。
- また外部のゲストをお招きして社内でインナーソースのイベントを開催してみるのも良いアイデアだと思いました。
InnerSource対談
ican.lab代表 (品質管理エキスパート)
熊川 一平 (Ippei Kumagawa) 様
株式会社 東芝 デジタルイノベーション技術センター
小林 良岳 (Yoshitake Kobayashi) 様
大企業でインナーソースを推進した経験とその活用方法について、対談形式で語られたセッションでした。
熊川様からは、どのようにしてインナーソースの考え方に辿り着いたのかという経緯が紹介されました。開発標準やビジネス標準などの規程類のドキュメント作成において、インナーソースの知見を活用した改善事例についてもお話しされていました。
また、品質の観点から見たインナーソースの効果についても言及されていました。
感想
瀧山:
- 開発標準や規定のようなものはみんな嫌い、だから利用者自身が使いやすいようにコントリビュートするというのは面白かったです。
添野:
- 規程類は確かにインナーソースの手法が効果的だと感じました。
- ファーストペンギンだけでなく、ファーストフォロワー(活動に賛同してくれる最初の人)も大切にしようという考え方に深く共感しました。
インナーソースヒーローからのメッセージ
KDDIアジャイル開発センター
インナーソースヒーロー / 中島 智弘 様
インナーソースヒーローからビデオメッセージが届き、それを視聴するセッションでした。
一人ひとりが所属組織を選択する時代に“われわれはなぜここにいるのか“その表現へのこだわりとプロセス
KDDIアジャイル開発センター株式会社スクラムマスター
泉本 優輝 (Yuki Izumoto) 様
登壇資料:
KAGreementとは、KAG(KDDIアジャイル開発センター)が憲章を社員それぞれで分解・解釈し、自分たちの働き方として再定義していく取り組みで、この手法を「KAG + Working Agreement」、略して「KAGreement」と呼んでいるそうです。
このKAGreementにおけるプロセスと、インナーソースのパターンを比べてみた際に、意外と共通点があったらしいです。
感想
瀧山:
- 社訓や行動指針のようなものは形骸化してしまうことも多いですが、全社員が取り組めるような仕組みができているのがすごいと感じました。
添野:
- 透明性を高く保ち、オープンなコミュニケーションの文化を築いている点が素晴らしいと感じました。
スケールする組織の実現に向けたインナーソース育成術
チームラボ株式会社 パッケージチームエンジニア
松本 玲音奈 (Leona Matsumoto) 様
登壇資料:
登壇者の自社のチームラボでのインナーソース活動を例にして、社内でどのようなSTEPでインナーソースを広めていく方法を紹介したセッションでした。
感想
瀧山:
- これまでは既存リポジトリをインナーソース化するパターンが多いかと思っていましたが、新規の便利ツールのようなものをインナーソース化するのはいいなと感じました。
添野:
- 「このツールを利用中のリポジトリ」のリンクを設けるのは、非常に効果的だと思いました。どのように利用されているかは、コントリビューター目線では気になるポイントであるため、こうした可視化により貢献へのモチベーション向上に繋がると感じます。
次のOSTの前に本イベントでのベストスピーカー賞の投票がありました。
ベストスピーカー賞の賞品としてウィンナーとマスタードソースが贈られていました。

InnerSource OST (Open Space Technology)
参加者から「このテーマについて他の人の意見を聞いてみたい」「本イベントでもっと深く話し合いたい」「次回のイベントで取り扱ってほしい」といった8つのテーマを募集し、それぞれのテーマごとに会場を分けてOSTの原則に従ったディスカッションセッションを実施しました。
また「チャタムハウスルール」が適用されているため、議論の場では自由に発言ができます。
感想
瀧山:
- 私はまだインナーソースを実践できていませんが、すでにかなり実践されている方の話を聞くのは面白かったです。初心者の疑問も話題にすることができました。
添野:
- OSTは初めて参加しましたが、色々とテーマについて他の会社の状況なども交えながら話せてとても楽しく良い経験になりました。
全体を通しての感想・学び・気付き
瀧山:
- 社外イベントに参加するのは久しぶりでしたが、熱量を感じるセッションばかりでとても刺激を受けました。社内で気になるインナーソースのリポジトリを見つけて、実際にコントリビュートしてみたいと思いました。
添野:
- イベントに参加してみて、インナーソース活動の新しい観点での気付きがあったり、会場の雰囲気自体もとても雰囲気が良かったため、次回開催されるのであれば、ぜひおすすめのイベントです。
終わりに
弊社では、外部のイベントやセミナーで学びを得られ、得た学びを持ち帰って周囲に共有できるのであれば上司の許可のもと自由に参加することができます。