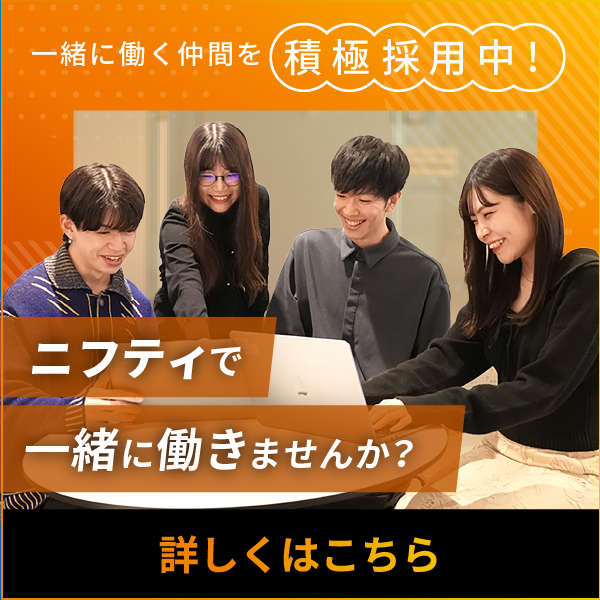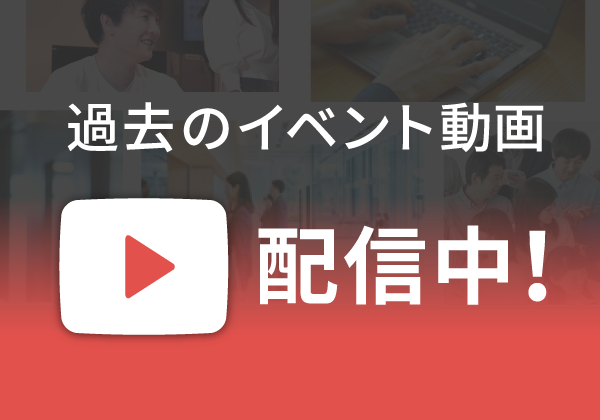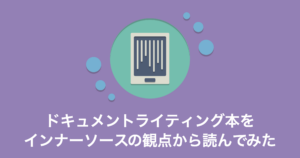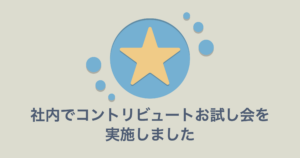オープンスペーステクノロジー(OST)を社内と社外でそれぞれ実践した二人の司会者による対談記事です。どちらも10人規模で行われたOSTですが、 テーマは違えどOST自体に対する成果や課題には興味深い違いがありました。
はじめに
オープンスペーステクノロジー(Open Space Technology、以下OST)は、参加者が自由にテーマを出し合い、自発的に話し合う場を作る手法です。
「4つの原則」があります。
- ここにやってきた人は、誰もが適任者である
- 何が起ころうと、それが起こるべき唯一のことである
- いつ始まろうと、始まった時が適切な時である
- いつ終わろうと、終わった時が終わりの時である
要するに、上下・役割関係なく誰でも参加していいし、OSTで話されることは全部学びとなる。また、いつ話し出してもいいし、いつ話を終えてもよいです、ってことです。めっちゃいいね、ってことで特に技術勉強会やテックカンファレンスの中でよく行われる場の作り方になります。
詳細は、「オープンスペーステクノロジー(OST)」でググってみてください!(他にも蜂とかキリンなど、4 つの役割なんてのもあります。)
今回は、社外コミュニティと社内チームでそれぞれOSTを実践した芦川(私)と西原さんに、その違いについて雑談したことがあったので、それをネタに対談風に記事にしました。
司会者プロフィール

芦川:InnerSource Commons Japan Meetupで「チームの壁、ぶっ壊そ!壁の乗り越え方、一緒に考えよう!」というテーマのOSTを主催。インナーソースの実践者コミュニティでのファシリテーターを務める。(InnerSource Commons Japanは、InnerSource Commonsの日本ローカルコミュニティです。OSSの開発の仕方・コミュニティの形成方法などいいところを社内に取り入れようぜ、というものです。)

西原:社内で「職場での悩み事」をテーマにしたOSTを実施。労働組合の執行委員長という立場から会社内のコミュニケーション活性化や関係性醸成に取り組む。
対談
― それぞれのOSTのテーマと参加者層について教えてください
芦川:社外OSTでは「インナーソース 組織内の壁と感じていることはなにか?」という大テーマで開催しました。参加者は約10名で、インナーソースに関心がある、あるいは既に実践している方々が集まりました。業界も会社も違う方々が集まり、「上下関係の壁」「チーム間の利害関係」などについて議論しました。資料は公開しておりこちらです。
西原:社内OSTでは「職場での悩み事」という大テーマで、運営サイドもあわせて10名ほどが参加しました。OSTそのものの馴染みが薄いと思っていたのでイベントタイトルを「ユニオンカフェ」とし、「抱えてるモヤモヤ、誰かと話し合ってみませんか?」という謳い文句で「OST」という単語はあまり出さずに募集をしました。テーマとしては「新規事業について」「今後のキャリアについて」「評価の上げ方」など、かなり具体的な職場の課題が挙がりました。全一般社員を対象にしたのですが、参加者の大半がエンジニア職でした。このあたりはイベント参加に対する部署ごとの文化の差もあったのかなと思います。
― 参加者の積極性や議論の深さやオープンさに違いはありましたか?
芦川:社外の場合、みなさん自発的に参加されているので、積極性が高かったですね。特に「インナーソースについて知見がある人・何らかの形で実践している人・悩みを抱えている人が集まった」ので、非常に濃い議論ができました。新しい参加者と運営の方の人数バランスも良かったと思います。会社名や具体的な事例を出しながらも、比較的オープンに話せる雰囲気がありました。異なる会社の方々だからこそ、「こうしたら解決した」「うちではこうしている」といった経験を率直に共有できたと思います。
西原:社内の場合は少し違いました。社内のセミナー用会議室を借りての開催でしたので「とりあえず来てみた」という声もあり、参加の動機が様々でした。セッションがスタートすると、どの卓も活発に議論がされていました。
芦川:印象に残ったセッションとかありました?
西原:自分も参加したのですが、営業の方が出した「エンジニアにやりたいことを伝えるには」というテーマのセッションが印象的でした。エンジニアには「これをやりたいです」と伝えるより「これってどうやったら実現できますか?」って聞くほうが前のめりになりそうという話で盛り上がりました。ただ、ここで1つ気づきがありまして、同じ社内でバックグラウンドが共通しているほうが議論しやすいだろうと思っていたのですが、むしろ社外の人同士のほうが後腐れがないため、深く話せるのではないかということにも気づきました。これは正直なところ盲点でした。
芦川:いや、そうかもしれませんね。社外OSTでは、もともとの人間関係が薄い分、悩みだけにフォーカスすることができて深く相談できる、なんてことはカウンセラーに相談する、とかそういったことに近いのかも。
西原:もう少し人数が集まるかなと思っていたんですが、参加者募集時に「職場での悩み」の例として挙げたものが「キャリアプラン」や「チームビジョン」などで、重たい印象を与えて参加のハードルをあげてしまっていた可能性もあります。もっとライトな例を多く用意してもよかったかもしれません。
― 場の雰囲気づくりで工夫した点はありますか?
芦川:社外OSTではWeWorkという場所を選び、ドリンク(ビールも!)を用意したのが好評でした!「ビール飲みながらは最高」「場所の静かさ・ゆるさ(空気感)など、非常に良かった」という声がありました。リラックスした雰囲気が対話を促進したと思います。
西原:芦川さんの社外OSTを参考に、こちらもアルコールを含めたドリンクと、あとはサンドイッチやおにぎりなどの議論の合間に片手で食べられる軽食を用意しました。食べることに集中してしまわないように箸やフォークが必要なオードブルなどは避けました。開始まではゆるめのBGMを流したりしたのですが参加人数が少ないこともあってか最初は少し重ための空気でした。
芦川:なるほどね、BGM。場作りはほんと大事ですよね。WeWorkはそもそも普通にコワーキングスペースとして働いている方がいる中だったので、カフェのような生活音があるような感じでした。そこもよかったのかもしれない。
西原:そうか、社内OSTであってもコミュニティスペースなどすこし広い場所でやってもよかったのかな。途中参加してもらえる人もいたかも。
― セッションの進め方に違いはありましたか?
芦川:社外OSTでは「1セッション35分(議論30分、発表5分)はちょうどよかった」という評価を得ました。また、2セッション目では「その場の流れで深追いしたいところについてテーマを新しく作成した」という柔軟な対応も行いました。ただ、司会者側がここ深堀りしたいと決めてしまったところがあり、これはよかったのか悪かったのか。
西原:社内OSTでもほぼ同様の時間配分でしたが、テーマが「昼食の場所や宴会のお店選び」から「キャリアプランの悩み」まで幅広く、時間配分の調整が難しい場面もありました。また今回一般参加者が少ないことから私含め運営側も全員セッションに入ってしまったことで、厳密なタイムキープが出来なかったのは反省です。
― OST実践から得た最大の学びは何ですか?
芦川:「InnerSourceという同じ軸でも、悩み方の軸に対する考え方は多様だ」という気づきが大きかったです。また、参加者からは「定期開催したい!」という声もあり、継続的なコミュニティ形成の場としての価値も感じました。
西原:「社内の知らない人に悩みを話すことのハードル」に対する認識を得たのと「部署によって文化に差がある」ことを再認識しました。他には「悩み」や「モヤモヤ」というマイナスのテーマで募るより、「いまの職場環境をよりよくする方法」のようなプラスのテーマで検討するべきだったかと思いました。ただ、参加者からは好評の声も多く聞こえたので次回につなげたいと思っています。
― お2人お話ありがとうございました!では、社内・社外OSTのお話から、今後のOST開催に関する成功要因をまとめてみたいと思います。
これがOSTの成功要因!!
意欲ある多様な参加者を集める
- 自発的に参加しようとする人が多いほど議論は活発になる。
- 異なる部署・会社・業界の人が集まると、率直な意見交換や具体的な経験共有がしやすい。
- 新規参加者と運営メンバーの人数バランスがよいと安心感が生まれる。
適切なテーマ設定
- 社外OSTでは「組織の壁」という抽象度のあるテーマで広がりのある議論が可能になった。
- 社内OSTでは「職場の悩み」をテーマにしたが、例示された議題の重さと社内の人に話すことに対する心理的ハードルなどもあり参加者が増えにくかった。
- ライトなテーマや具体例を混ぜることで、参加のハードルを下げられる。
安心感ある場づくり
- 社外OSTでは人間関係が希薄なため、むしろ率直に悩みを深く話しやすかった。
- 社内OSTでは関係性が近い分、テーマによっては話しにくさが出る場合がある。ここはテーマ選びをちゃんと考える必要がある点。
- WeWorkといった快適な場所選びやドリンク(ビール含む)の用意が好評。
- 静かでゆるい空気感が対話を促進し、意見交換を自然に進めやすくした。生活音があるような空間がよいのかも。
- クローズドな場よりもオープンな場がよさそうだ。
まとめ
社外と社内、どちらが良いということはありませんが、OSTは場のデザインによって大きく成果が変わることが今回2つのOSTの結果を比較することでわかりました。
みなさんもOSTを実践する際には、「参加者」「テーマ」「場」の特性を考慮したデザインを心がけてみてください!!
OSTめっちゃいいですよ!!