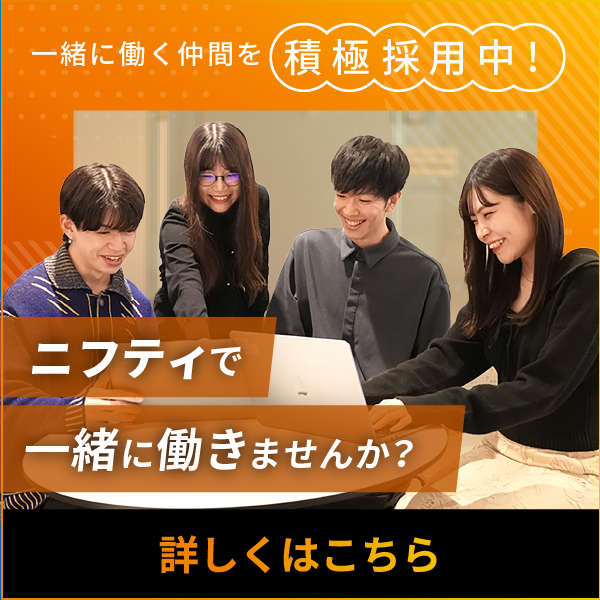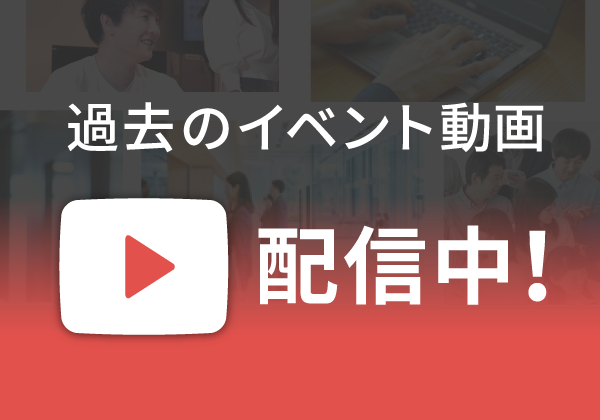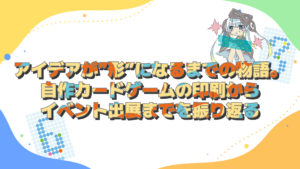こんにちは!Maker Faire Tokyo 2025 リレーブログのバトンを受け取りました、西根です。
普段はニフティポイントクラブの開発・運用を担当していますが、プライベートではボードゲームで遊ぶのが大好きです。
そんな「ただのボードゲーム好き」な私が、今回ひょんなことから Maker Faire Tokyo 2025 に出展するオリジナルカードゲームのルールデザインを担当することになりました。
この記事では、専門知識ゼロの私たちが、どうやって「面白い」の核となるゲームルールを作り上げていったのかのプロセスをご紹介します。
ステップ1:ゲームの方針決め
何から手をつけるべきか全くわからなかったため、まずは「ボードゲーム 自作」などで検索し、先人たちの知恵が詰まった記事を数本読み漁るところからスタートしました。
なんとなく流れを掴んだところで、社内のボードゲーム好きな関係者を集めてキックオフミーティングを開催。
ここで、プロジェクトの「骨格」となる重要な方針を決めました。
1. コンポーネントを決める
「どんなゲームにするか」の前に、まず「何が作れるのか」という現実的な制約を確認しました。
事前にいくつかの印刷所を調べ、予算と納期、そして「ゲーム制作の難易度(=コンポーネントの複雑さ)」を考慮し、今回は「カード」をメインにしたゲームに絞ることにしました。
2. 対象ユーザーを決める
ゲームの難易度を決める上で、これは非常に重要な指標です。
Maker Faire Tokyoの参加者は半分近くが親子連れというデータを参考に、「持って帰って家族でも遊べると良いよね」という話になりました。
- プレイ人数: 2〜4人
- 対象年齢: 小学5年生〜くらい
(ちなみに、当日は想定より小さいお子さんもたくさん遊んでくれました!これは別の記事で詳しく書きますが、事前に「小さい子にはちょっと複雑かも…」という意見を受け、簡略化ルールを考えておいたのが功を奏しました)
3. テーマ・体験を決める
せっかくニフティとして出すからには、「ネットワークやITに関連するテーマにしたい」という共通認識がありました。
また、ゼロから独創的なゲームシステムを考えるのはハードルが高いため、「既存のカードゲームやトランプをベースに、ニフティらしさをアレンジする」という方向性で話し合いました。
最終的に、ニフティという社名にちなんで、手札の合計値が22になることを目指すブラックジャックのようなゲームにすることに決定しました。
この日は、その場で既存ゲームをベースにしたアイデアをいくつか出し合い、解散となりました。
ステップ2:テーマとタイトル決定
次の打ち合わせでは、前回出たアイデアを3案に絞り込み、カードデザインの難易度や懸念点を考慮しつつテーマを何にするか話し合いました。
ソフトウェア開発(スクラム開発)に寄せるか、家庭内ネットワークに寄せるかなど議論がありましたが、インターネット通信について興味を持ってもらうきっかけになって欲しいという思いから、ニフティの主力事業である「ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)」に絡めたゲーム案に決定しました!
タイトルはAIと多数決で
テーマが決まればタイトルも必要です。ここでは生成AIが大活躍しました。
私たちが考えたゲームの概要をAIに渡し、とにかく大量のタイトル案を出してもらいました。
その中からキャッチーで良さそうなものを3つに絞り、ボードゲームに興味がある社内の人たちに投票してもらって決定。(面白いことに、投票結果はかなり偏り、「やっぱりこれが良いよね」と最初に盛り上がっていた案に収束しました)

ステップ3:ひたすらテストプレイ
ルール案の大枠ができたら、あとはひたすらテストプレイです。「面白くなかったら修正」を地道に繰り返しました。
1回目:身内(デザイン・イラスト担当)
まずはプロジェクトメンバーのうち、コンポーネントに関係する人で実施しました。
まずはゲームの流れを確認し、社内のカードゲーム好きな人にゲームバランスの取り方などを聞きつつ、ターン数は有限にするのか、特殊カードの割合はどのくらいにするかなどを1から決めていきました。
2回目:外部(企画担当、無関係な人)
次に、このプロジェクトに全く関わっていない人も含め、別の人に遊んでもらいました。
ルール説明が伝わるか、直感的に面白いか、客観的な意見をもらう絶好の機会となったので、ルールデザイン中に実施してよかったです!
ルールの「解像度」を上げる
ゲームを盛り上げるイベントカードにはISPらしさを持たせたかったので、実際にISPチームの人に「トラフィックが増えるイベントって具体的に何があります?」とヒアリングし、カード名にリアリティを持たせました。
最後は、AIにルールブックの草案を整形してもらい、ルールの穴や矛盾点がないかを客観的にチェックしました。(それでも後に穴が出てきたりはしましたが…)
ルールデザインを終えてみて
今回、ルールデザインという大役を(勢いで)引き受けましたが、終わってみて感じたのは以下の3つです。
- 意外と初心者でもルールは作れる!
既存のゲームをベースにすることで、面白さの土台が担保されるため、初心者でも十分に楽しんでもらえるゲームルールを作ることは可能でした。
- 「作り手のバイアス」を捨てる
これが一番大事かもしれません。自分が作ったゲームは「ここが面白いだろ!」というバイアスにかかりがちです。テストプレイでは、とにかく素直に意見を聞き入れ、「どうするともっと面白くできるか?」を深掘りする構えが必要だと痛感しました。
- AIは最高の壁打ち相手 タイトルの案出しやルールの穴探しなど、人間の思い込みを排除したい作業において、AIは最高のパートナーでした。AIをフル活用したことで、短時間でクオリティを上げることができたと思います。
なにより、当日のアンケートで「ルールが面白かった」というコメントを見つけた時は、本当に嬉しかったです!
「ただのボドゲ好き」がどこまでやれるのか不安でしたが、挑戦して本当に良かったと思っています。
次回は、西野さんによる「ISPがつくる、カードゲームのデザインができるまで」です!